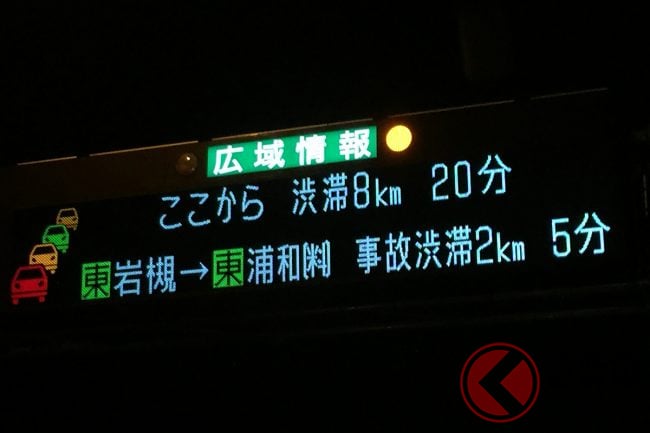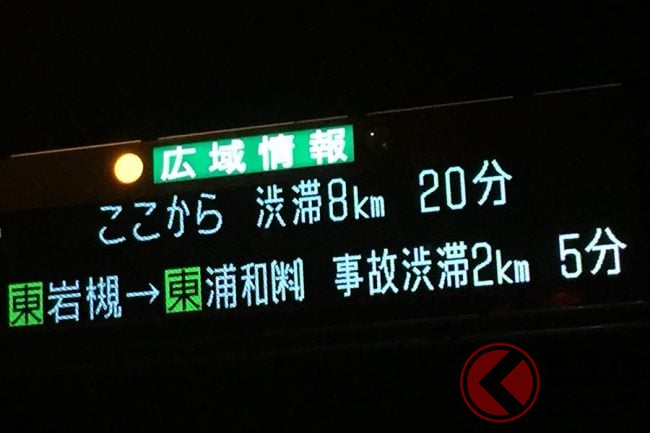なぜ道路脇に「ツツジ」が多い? 高速道も緑化進む? 目の保養だけではない「安全」に欠かせない理由とは
普段、道路を走っていると、中央分離帯や道路脇にずらりと並ぶ緑が目に入ることがあります。当たり前の風景として見過ごしがちですが、実はそこには意外な理由が隠されています。
安全運転を支える存在だった!植物の意外な役割
一般道や高速道路を走行していると、中央分離帯や側道にずらりと植えられた植物が目に入る場面がよくあります。
あまりに見慣れた光景のため、なぜそこに植物が植えられているのか、あらためて疑問に思うことは少ないかもしれません。なぜ低木(ていぼく)から高木(こうぼく)まで様々な植物が植えられているのでしょうか。

一般道の脇に植えられた植物には、高木(高さが5m程度を超える樹木)で「イチョウ」や「サクラ」「ケヤキ」など、中低木で「ツツジ」などが有名で、これらは景観などの問題も含め落葉広葉樹(冬場や乾季に葉を落とす広葉樹)が好まれています。
地域的な特色がありその土地ごとに自生の種をそのまま使おうという動きが盛んです。
例えば北海道では「エゾマツ」、「ナナカマド」、「カエデ」などが高木樹種の上位を占めるほか、東北から関東や北陸では「ケヤキ」、「イチョウ」、「サクラ」が植えられています。
また西日本の近畿や中国、四国地方では「モミジバフウ」、「クスノキ」など暖かい地域の高木が増加。
沖縄では、「フクギ」、「リュウキュウコクタン」、「リュウキュウマツ」と他県との違いが顕著となっています。
一方で中低木に関しては、ほとんどの地方で「ツツジ」が多くなり、過酷な環境に耐えられ、やせている地でも虫がつかず美しい景観を保ち、さらに空気清浄効果も。
さらにツツジは、シックハウス症候群でも悪名高い「ホルムアルデヒド」を吸収し、空気を浄化してくれる働きがあることでも知られています。
では、高速道路にはどのような植物が植えられているのでしょうか。以前にNEXCO東日本は次のように説明していました。
「高速道路では、背の高い種類として『アカマツ・クロマツ類』『スギ類』などの常緑針葉樹(年間を通して葉をつける樹木)、『コナラ』『サクラ』などの落葉広葉樹が多いです。
中低木では、『ツツジ類』『ハギ類』、地被植物(地表を覆うタイプの樹木)では『ヘデラ類』が多いなど、一般道とは植えられている樹種にやや違いがあることが挙げられます。
ヘデラとは、別名『アイビー』『セイヨウキヅタ』などと呼ばれるツル植物で、とくに高速道路の車道に接する箇所や壁面の緑化に利用されています。
これらの違いは、高速道路が土の造成箇所では法面を有すること、視点の移動速度が一般道と比べて大きいといったことが要因と考えられます」

さらに具体的な効果として「視線誘導や遮光により走行環境の改善や地吹雪防止などの交通安全向上機能」が挙げられています。
たとえば、夜間に対向車線から飛んでくるヘッドライトの光がまぶしくて視界が遮られるという経験をしたことがある人も、少なくないかもしれません。
そんなとき、中央分離帯に植えられた植物が視線の遮へい物となり、対向車のライトの直接的な光をやわらげてくれます。これにより、ドライバーは適切な視界を確保しながら、安全に運転を続けることができます。
また、カーブが多い山間部の道路では、中央分離帯の植物の並びを見ることで、これから道がどの方向に曲がるのかを視覚的に把握しやすくなります。
とくに高速道路はスピードが出やすいため、あらかじめ道路の線形を認識できることは大きな安全対策となります。
さらに、中央分離帯の植栽は、単調になりがちな道路風景に変化をもたらす役割も担っています。
郊外の直線的なルートや、まっすぐな高速道路では、同じような景色が延々と続き、運転に対する集中力が切れがちです。
そこで、緑が目に入ることでドライバーの意識がリセットされ、眠気や注意力の低下を防ぐ効果が見込まれているといいます。
またNEXCO東日本によれば「高速道路の緑化は、地球温暖化防止や生物多様性などの『環境保全機能』や、季節感豊かな走行環境を創出し周辺環境との調和を図る『景観保全機能』を持っています」と言います。
日本の高速道路は、山を切り開いて造られているケースが多く、クルマが発する二酸化炭素が周囲に排出されます。
そこで、二酸化炭素を吸収する植物を植えることで、少しでも自然との調和を図ろうとする試みがなされています。
加えて、防音壁やコンクリート構造物といった無機質な風景を和らげる効果もあり、より快適で落ち着いた走行空間を演出する役割も果たしています。
こうした取り組みは、サービスエリアやパーキングエリアの緑地整備にもつながっており、休憩中のリラックス効果にもつながっています。
※ ※ ※
高速道路の中央分離帯に並ぶ植物には、ドライバーの安全を守るための多くの工夫が詰まっています。
視界を確保するための遮光、道路形状の視認性向上、単調な景観へのアクセントなど、その存在は決して「飾り」ではありません。
選ばれている植物も、常緑で手入れしやすく、高くなりすぎないものが中心。
走行中には気づきにくい存在かもしれませんが、その裏には道路の安全性と環境への配慮がしっかりと行き届いています。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。