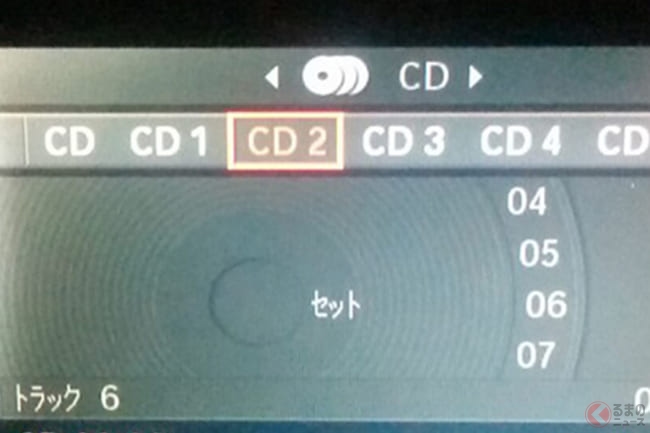「うわぁ!懐かしい!」 “腕回しバック駐車”は過去の話? 昭和で当たり前だったけど“令和で消えそう”な「クルマ運転あるある」5選!
クルマを動かすうえで必要だったさまざまな行為が、テクノロジーの進化やハイテク装備の普及により不要になってきています。今ではすっかりやることが少なくなった、運転にまつわるあれこれを振り返ります。
もはや絶滅寸前!? 消えつつある運転の行為5選
昭和、平成、令和へと時代が移り変わり、クルマ業界を取り巻く環境も目まぐるしく変化しています。
電動化、運転支援システムなど先進的な技術が普及するその陰で、20〜30年前まで当然のように行われていたさまざまな行為が時代遅れになりつつあります。
そんな今ではほとんどやる必要がなくなった、クルマの運転動作について紹介します。

●パーキングブレーキをかける行為
パーキングブレーキは主に、サイドブレーキと呼ばれることの多い「レバー式」と「足踏み式」に大別されています。
ほかにもトラックをはじめとする商用車に多い「ステッキ式」も存在します。
そんな手動式パーキングブレーキですが、ボタン1つで動作する「電動パーキングブレーキ」の登場により存在感を失いつつあります。
国産車では2006年登場のレクサス「LS」に初めて搭載され、2010年代になって採用車種が増加しました。
シフトをPレンジに入れると自動で作動する場合や、ブレーキペダルから足を離しても停止したまま保ってくれる「オートブレーキホールド機能」を備えている場合もあります。
全車速追従型クルーズコントロールの搭載車種は、先行車が停止したら自動で停止し、ブレーキをホールドさせ続ける必要があります。
電動パーキングブレーキが広がっている理由の1つに、こうした先進装備への対応が考えられます。
●バック時に後ろを見る行為
バック駐車する際に助手席に手を回す、いわゆる「腕回しバック駐車」や、窓を開けて後方を目視で確認する行為は、かつての風物詩となりつつあります。
バックモニターや360度モニターの普及により、こうした目視確認の機会が激減しています。
車両後部に設置されたカメラの映像を表示するバックモニターは、1990年代後半に普及しはじめました。
2024年11月からは新型車・継続生産車を問わず、全ての車両にバックモニターまたはソナーなど検知システムの装着が義務化されています。
さらに、複数台のカメラを組み合わせ、上空からクルマを見下ろしているような映像を映し出す360度モニターの登場も市場に大きなインパクトを与えました。
日産は2007年に「インテリジェントアラウンドビューモニター」をエルグランドに装備し、世界で初めて実用化。
トヨタは「パノラミックビューモニター」という名称で導入し、他のメーカーも追従しています。
●自分でシフトチェンジする行為
1990年代前半、AT限定免許を取得する人は限られており、なかにはMT車を運転できないことに引け目を感じる人も少なくありませんでした。
ところが、AT車の比率は1990年代から上昇を続け、2016年における新車に占めるAT車の割合は約98.4%、2019年には約98.6%に上昇(日本自動車販売協会連合会調べ)。
ATやCVTの登場はもちろんのこと、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド)のように変速機のないクルマも増え、手動でシフトチェンジを行うMT車は絶滅の危機に瀕しています。
スポーツカーについても例外ではなく、変速ショックが少ないDCT(デュアルクラッチトランスミッション)が採用される代わりに、3ペダルを備えたMT車の選択肢は用意されなくなってきています。
2022年登場の新型「フェアレディZ」に6速MTが用意され話題になりましたが、純MT車は今後ますます貴重な存在になることでしょう。