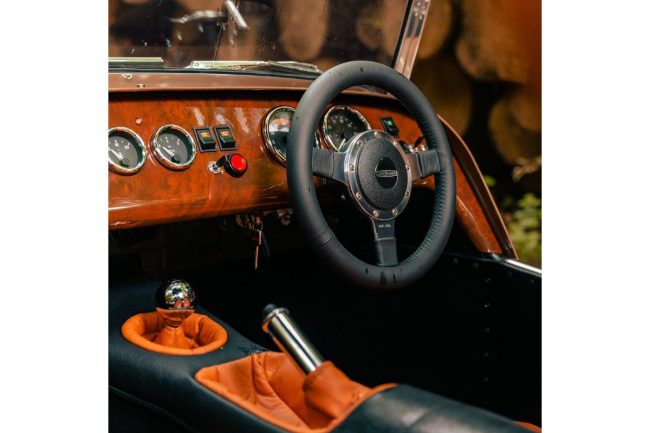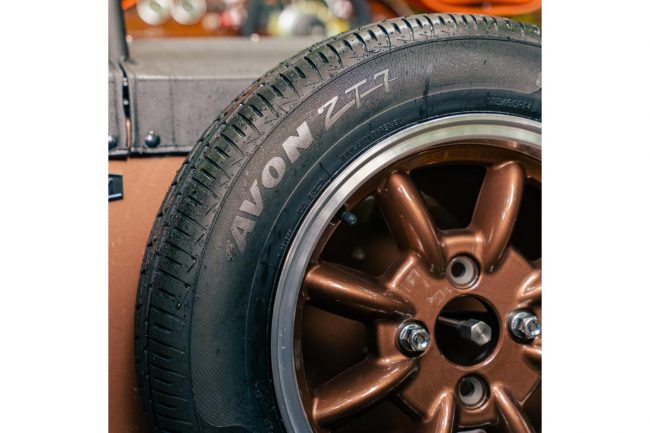「軽自動車」はいつから始まった? 日本の知恵と技術が詰まった「76年の歴史」と発展とは
経済的で小回りの利く移動手段として多くの人に利用されている「軽自動車」は、一体どのように進化してきたのでしょうか。
軽自動車の歴史とは
軽自動車は、今や日本人の「暮らしの足」として欠かせない存在です。経済的で小回りの利く移動手段として多くの人に利用されています。
外国にはない日本独自の規格ですが、一体どのように進化してきたのでしょうか。

日本における軽自動車の歴史は、終戦後の法改正の中で誕生しました。1949年に軽自動車の規格が制定され、従来の小型自動車が「小型自動車」と「軽自動車」に分割されたのが始まりです。
戦後の日本経済の再建期において、軽自動車は手ごろな価格で購入できる車として必要とされました。しかし、実際に生産が始まり市場で日常的に見られるようになるまでには、約10年の年月がかかっています。というのも、国内で技術を発展させるために、海外の技術を学ぶ必要があったからです。
1955年頃になってやっと、鈴木自動車工業(現:スズキ)、ダイハツ工業、富士重工業(現:SUBARU)、東洋工業(現:マツダ)、新三菱重工業(現:三菱自動車工業)といった軽自動車メーカーが出そろい、本格的に生産が開始されました。
日本初の量産軽自動車となるスズキの「スズライト」が発売されたのもこの年です。
3年後の1958年には、富士重工業が「スバル360」を発売。完成度の高さと42万5000円という価格設定は、個人が乗用車を所有するという新しい需要を生み出しました。
これらの出来事は1950年代後半から1960年の高度経済成長期に重なり、個人の所得が増加して自動車の所有が広がる中で、軽自動車の需要が本格化していきました。
※ ※ ※
1949年の規格制定当時の軽自動車は「長さ2.80m以下、幅1.00m以下、高さ2.00m以下」でした。現在の規格が「長さ3.40m以下、幅1.40m以下、高さ2.00m以下」であることを考えると、かなり小さいことがわかります。
翌年の法改正で四輪・三輪・二輪の区別が定められたのをきっかけに、三輪および四輪の軽自動車は「長さ3.0m、幅1.30m、高さ2.0m、排気量は350cc」まで拡大されました。その後10回以上の規格改正を繰り返し、1998年に現在の軽自動車の規格となっています。
1998年の改正では、衝突安全性基準が普通自動車・小型自動車と同一のものとなり、安全衝突基準も普通自動車と同様となったことで、定員4名以下、貨物積載量350kg以下という規格も新設されました。軽自動車の安全性は飛躍的に向上します。
※ ※ ※
軽規格制定から76年経った現在、軽自動車の保有台数は3000万台以上で、自動車総保有台数の約4割を占めています。そのうち、1日あたりの移動距離が20kmを下回るユーザーが半数以上、平日の平均乗車人数1.33人/台というデータも出ており、軽自動車は「少人数で近距離移動のユーザーのニーズを満たしている」といえるでしょう。
また、軽自動車のユーザーは64%が女性で、43%が高齢者です。このデータは日本国内での軽自動車の利用状況を示しています。軽自動車の女性ユーザーはすべての世代で就業率が高く、通勤や日常の移動手段として便利な存在です。
特に高齢者にとっての軽自動車は、暮らしの足として欠かせない存在となっているようで、現に高齢者ユーザーのうち66%が「軽自動車から普通車に切り替えるのは困難」と回答しています。
このように日本国内で高い支持を得ている軽自動車ですが、日本独自の規格のため、海外への輸出は容易ではありません。ただ、アジアや米国の一部の州では軽自動車の公道走行が可能で、特に軽トラックの使いやすさと手軽さが人気を博しています。
軽トラックといえば、バンタイプの軽自動車は、災害時の物資運搬や福祉車両として活躍しているのも知っておきたいところです。小回りのメリットを活かし、被災地の悪路走行や車椅子のお年寄りを住宅街の家の前まで送迎も可能です。
また、軽自動車の技術をベースとしたクルマは、インドネシア、パキスタン、マレーシアなどをはじめとするアジアの市場でも大きな存在感を示しています。アジアの国々では高速道路が少なく狭い道路が多いこと、燃費が良く価格が安いことなどが人気の理由となっています。
このように軽自動車の技術は国内だけにとどまらず、海外でも愛されていることがわかります。
TSUMUJI Writing Studio(きこ)