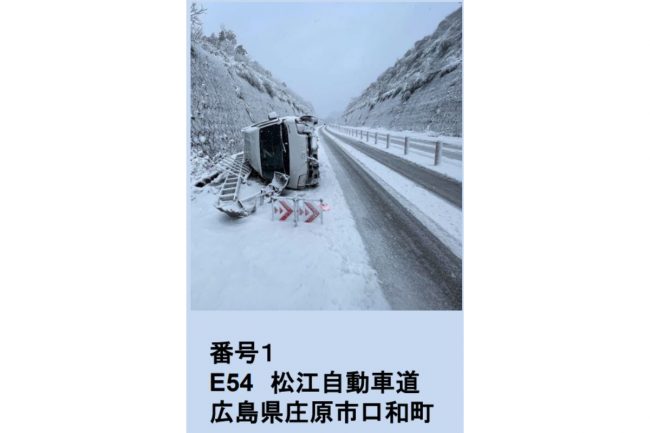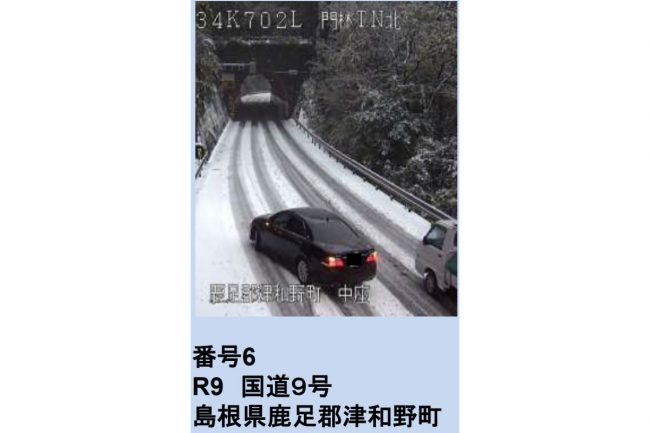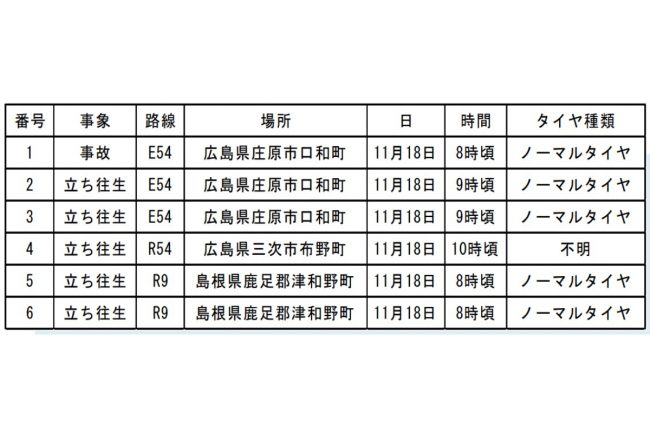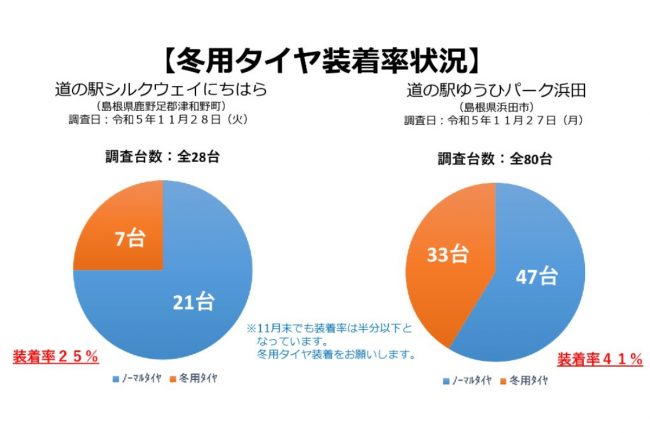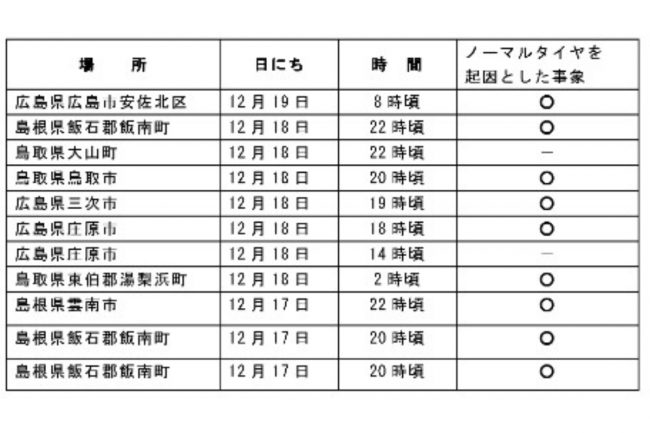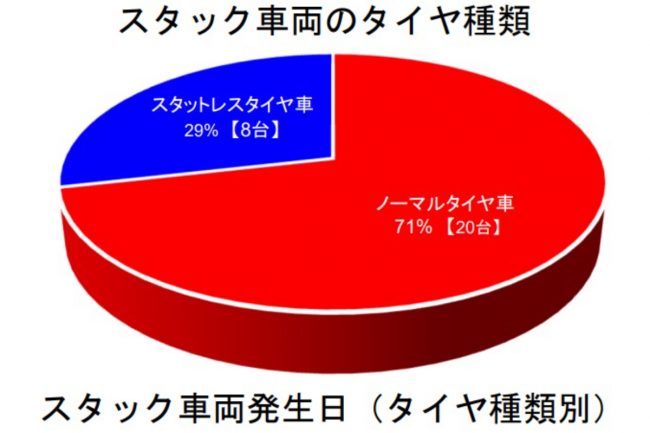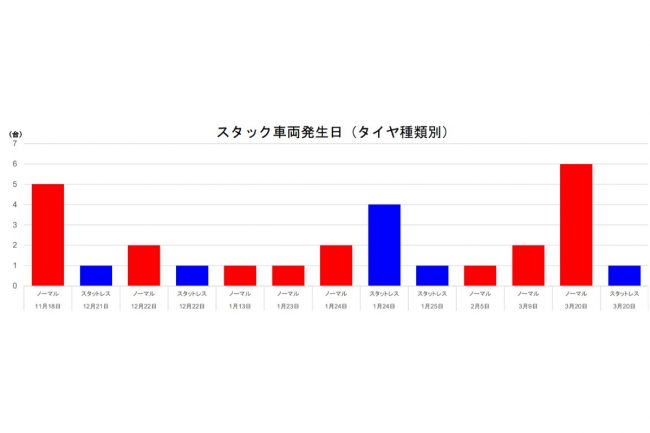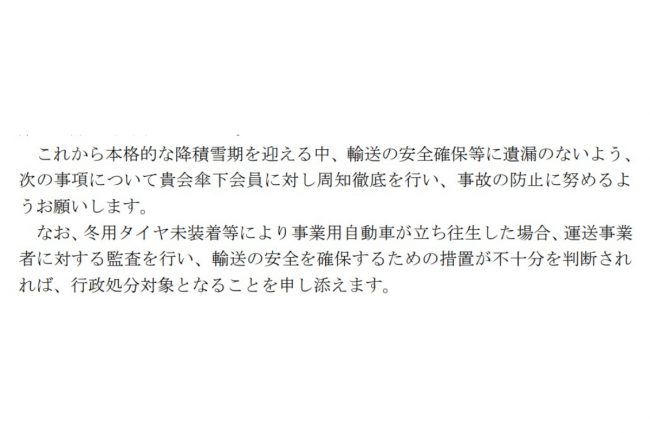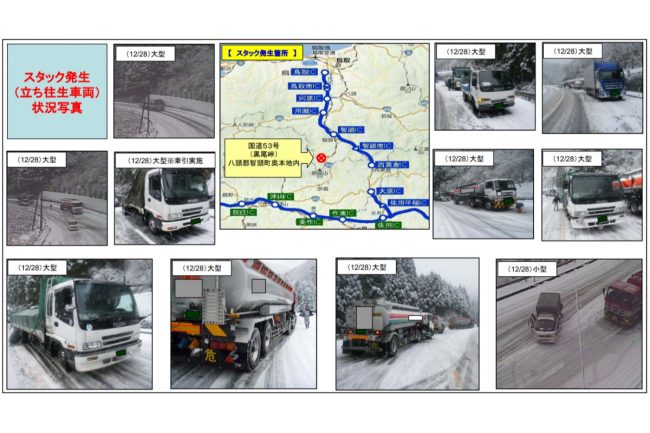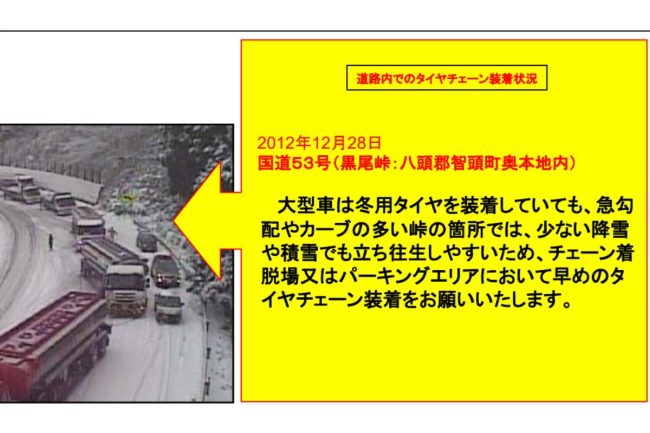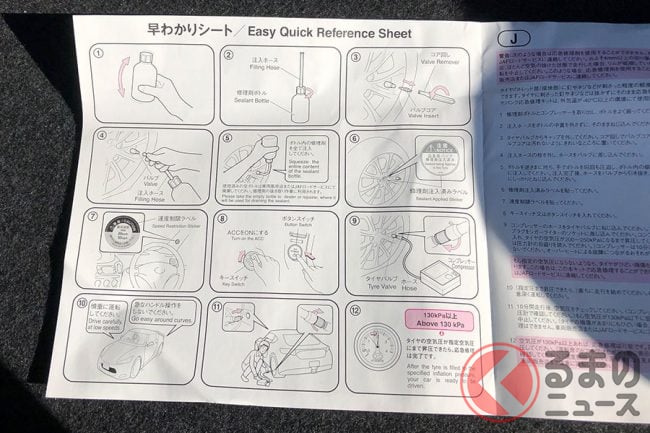「国道63号は何県にある?」が“超難問”である理由とは システムのバグに「異例の措置」も!? 謎多き“国道数字空白エリア”を生んだ「歴史的背景」
日本には数多くの国道が走っていますが、「国道63号」という国道は聞き覚えが無いかもしれません。実は存在しない国道番号は多数あります。なぜなのでしょうか。
「国道63号」ってどこ?
「国道63号はどこを走っているでしょうか?」という質問に、答えられる人はいるでしょうか。
全国の知人に聞いて回っても、「私の地元の近くには無いですね」という返答になるかもしれません。
一体どういうことなのでしょうか。

実は「国道63号」という国道は、日本のどこにも存在しません。
それどころか、二桁の国道番号の大半を占める「国道59号以降」は、すべて「欠番」になっています。「国道100号」すら存在せず、「国道101号」以降やっと実在する路線になります(ちなみにルートは青森~能代~秋田)。
なぜ国道番号が丸ごと飛んでいるのでしょうか。また、いつかはこの欠番が埋まる可能性はあるのでしょうか。
※ ※ ※
高速道路などを除外して、一般的に認識される「国道」というものは「一般国道の路線を指定する政令」によって設置・指定されるものです。
都道府県をまたいで県庁所在地や重要都市をつないだり、それら国道や高速道路への枝線として主要都市や重要な港湾、観光地、空港などからつないだり、国土の総合的な開発に資するものであることから、都道府県ではなく国が、整備方針を決めているのです。
さて、もともと国道は「一級国道」「二級国道」というクラス分けがなされていました。
一級国道は先述の冒頭に出てきた「都道府県をまたいで県庁所在地や重要都市をつなぐ」という、鉄道でいうところの「本線」的な役割を果たすものと位置付けられていました。
一級国道は1号から57号まで指定され、さらに将来的には58号、59号、60号、61号…と追加指定されるために空き番号が用意されていました。
それ以外の国道は二級国道として、101号、102号…と順次指定・追加されていくシステムでした。
ところが1965年に、一級・二級は統合されて、新たに「一般国道」という扱いになったのです。この時点では国道271号までありましたが、今後は重要度合いに限らず一律に272号、273号…と追加されることになりました。
そのため、一級国道があった時代の「さらに将来的には58号、59号、60号、61号…と追加指定される…」ということが、システム上半永久的に起こり得なくなり、実質的な「欠番」となっているわけです。
ひとつだけ例外で、沖縄県を走る「国道58号」だけは、1965年の「一般国道」移行のあとにこの数字が割り振られています。これは1972年の沖縄返還で日本の国道に所属することとなったという、複雑な時代背景があったようです。
※ ※ ※
ほかにも国道の欠番は109・110・111・214・215・216の6つがありますが、これらは指定変更や統合で、別の番号の路線へ切り替わって消えたものです。
Writer: くるまのニュース編集部
【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】
知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。