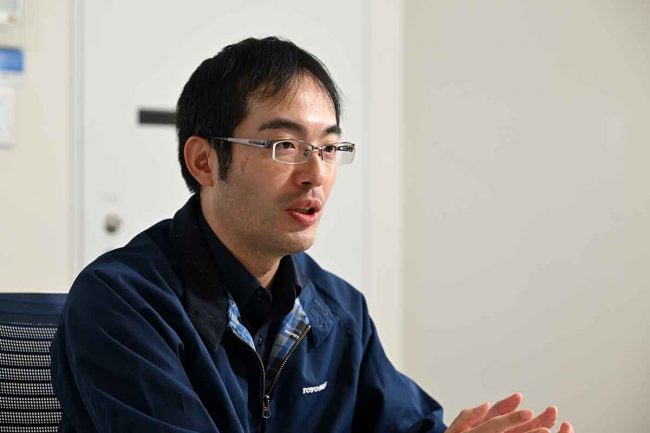ダカールラリー2024直前!「ランクル300」で市販車部門11連覇を狙うTLCとその走りを支えるトーヨータイヤの挑戦とは【PR】
2024年1月5日から19日まで、サウジアラビアで開催される「ダカールラリー2024」。トヨタ車体の「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー(TLC)」は、前回に引き続きトヨタ「ランドクルーザー300」で参戦、市販車部門11連覇を目指します。その走りを支えるのはトーヨータイヤ「OPEN COUNTRY M/T-R」。その開発者に話を聞きました。
市販車部門10連覇の偉業を達成するために苦労した点とは?
さて、トーヨータイヤがサポートし参戦2年目となるダカールラリー2023では、TLCの競技車両は200系ランクルから300系(以下、300系ランクル)にスイッチ。市販車開発時点からダカールラリーを見据えた新型車で、「市販車部門10連覇」の偉業に挑むことになります。

「ダカールラリー2022の終了直後に、それまでの競技車両に装着していたタイヤと同じ仕様のものを開発途中の300系ランクルに装着し、海外でテストを行いました。まず確認したかったのは同じサイズで大丈夫かということと、性能が向上した新型車にどれだけマッチするかということでした。
テストの結果は良好で、サイズも金型も変えずに、新型車にあわせたチューニングを施すという方向性が決まりました。前回大会で発生した熱によるトラブルに対応し、かつサイドウォールを強化して外傷によるパンク耐性も高めました。ただそのまま強化しただけではタイヤ単体の重量が重くなり、軽くかつパワーのある300系ランクルのよさを打ち消してしまうため、構造や形状の工夫などで従来モデルと同等の重量になることを目指しました」(松原氏)
 |
 |
|---|---|
こうした性能向上を目指す改良の一方で、ダカールラリー2023向けタイヤには、環境に配慮した設計も新たに採り入れています。トーヨータイヤ技術開発本部材料開発部タイヤ配合開発グループの久保西弘幸氏は、その取り組みを語ります。
「タイヤには、多くの石油由来素材が使われています。この石油由来素材を非石油由来素材、リサイクル素材、再生可能素材などに置き換えようというのが、当社の将来に向けた考え方です。ダカールラリー2023に向けたタイヤには、バイオマス由来の合成ゴム、再生素材のビードワイヤを使用しました」(久保西氏)

こうした素材の変更も、まずマテリアルズ・インフォマティクス(MI)を利用したゴム材料の特性予測技術により確認し、その後、実際にタイヤを製作して試験機で確認するという流れをたどります。
「ダカールラリー2023では、こうしたサステナブル素材が過酷な実戦で耐えうるのか確認することを目標としました。ただ材料開発の担当者として、サステナブルな素材を採用したことでタイヤの性能が低下し、それが原因で『市販車部門10連覇』を逃すことになったと言われることがないよう、十分に検討し、自信を持って送り出しました」(久保西氏)
そしてサステナブル素材を新採用した「OPEN COUNTRY M/T-R」は、久保西氏の自信どおり、所期の性能を発揮。TLCは市販車部門で優勝、10連覇を飾ります。

「ダカールラリー2024に向けては、サステナブル素材をさらに意欲的に採用する方向で、開発を進めています。具体的には籾殻(もみがら)の灰から取り出したシリカ、植物由来オイル、再生カーボンブラック、バイオマス由来のポリエステル繊維などです。
こうしたサステナブル素材は石油由来の素材とは特性がやや異なるため、そのまま置き換えるとタイヤの性能が異なるものになってしまいます。そこでその特性にあわせて細かいチューニングを施し、タイヤ全体として同等以上の性能になるよう工夫しています」(久保西氏)
こうした開発と知見の蓄積は、将来の市販タイヤへのサステナブル素材の導入に大きく役立つとのことです。
「サステナブル素材は原料自体が高価であったり、リサイクルの手間がかかるなど、現時点ではけっして安いものではありません。ただ研究開発を続け、性能だけでなく、コストの問題も解決して、将来の市販タイヤへの幅広い導入を可能にしたいと考えています」(久保西氏)
 |
 |
|---|---|
ダカールラリー2024ではサステナブル素材を使ったタイヤで結果を出す
最後に、間もなくスタートを迎える「ダカールラリー2024」への意気込みを聞きました。

「前哨戦となるモロッコラリー2023では、三浦選手とも相談の上、トレッドブロックを低くしたものを装着し、砂漠での走破性にしっかりとした手応えを感じました。先にも述べたように、ダカールラリーのコースは年を追うごとに難しくなり、想定以上の超低内圧で走らざるを得ないような状況も生まれています。そうしたタイヤに厳しい環境でも、しっかりと完走、そしてひとつでも上位を目指すことのできるタイヤの開発と現地でのサポートで、TLCを支援したいと思っています」(松原氏)
「タイヤの素材はある部分、地味な存在です。しかしこうした大きなレースでサステナブルな素材を使ったタイヤがきちんと結果を出すことができれば、大きな注目が集まると思っています。TLCのサポートを通じ、一般のお客さまにサステナブルな素材への関心、そしてそうした素材の導入に取り組む当社の姿勢をアピールできたらいいなと思います」(久保西氏)