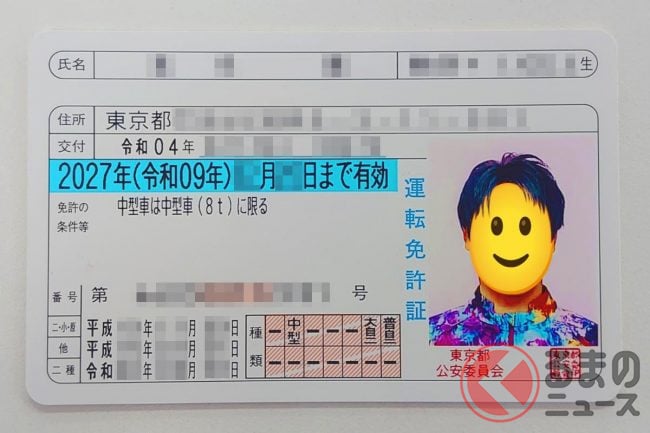クルマの「左寄せ」苦手な人多数!?「だってタイヤ見えないじゃん」どう対策? JAFが解説する「車両感覚」きたえる「練習方法」とは
多くのドライバーが苦手意識を持っている運転技術が、「クルマの左寄せ」かもしれません。左側面を壁にこすらずに、なおかつなるべく壁に近づけるコツは一体何なのでしょうか。
「車両感覚」をつかむコツはあるのか
多くのドライバーが苦手意識を持っている運転技術が、「クルマの左寄せ」かもしれません。
左側面を壁にこすらずに、なおかつなるべく壁に近づけるコツは一体何なのでしょうか。

左寄せが難しい理由は、日本のクルマは右ハンドルなので、運転席から左側の側面を目視できないという背景があります。
右側であれば、窓を開けて身を乗り出せば、クルマと壁の距離は目でしっかり見えます。しかし左側は、小さなサイドミラーをさらに遠くから見るしかなく、大変です。
じつはこうした技術は「車両感覚」が必要になってきます。
クルマと障害物、段差、崖っぷちに対し「目に見えないところで位置関係を把握する技術」と言えます。逆に言えば、直接見ないと互いの距離が理解できない人は、そもそも運転に不向きだと言っても差し支えないほどです。
そのため、教習所でも車両感覚はしっかりトレーニングを受けることとなります。その代表例が「S字」「クランク」です。クルマのボンネットが邪魔で、前輪が道路端へどこまで寄っているのか全く見えない状態で、脱輪リスクがどこまで高まっているか、どこまでさらに寄せられるかを、周囲の状況から「間接的に」判断する技術が必要となるのです。
その車両感覚が無ければ、周囲に相当な空間的に余裕が無いと、ろくにクルマを運転できないこととなります。常に大通りを走行しているわけではなく、日常生活では駐車場への駐車や、狭い路地でのすれ違いなど、必ず「車両感覚」が求められてきます。「だって難しいんだもん」「だって見えないんだもん」「私だって必死にやってるのに」は通用しないのです。
そうした悩みに対し、JAF(日本自動車連盟)は専用ページを設けて、この「車両感覚」を身に着けるコツを解説しています。
JAFいわく、まず大切なのは「繰り返しの練習」だといいます。頭で理論を暗記していても、身体が付いてこないというのは、クルマの運転だけでなくスポーツやどのフィジカルにも言えることでしょう。
具体的な練習方法ですが、助手席側(左寄せ側)の車両感覚をつかむ方法として紹介されているのが、「ライン」を実際に踏んでみて、その時の「周囲の見え方」の特徴を意識するというものです。練習は公道を避け、周囲に誰もいない適切な場所でやりましょう。
これはもちろん、最初に相方に「ちゃんとラインを踏めてるよ」と確認してもらうことが大切です。
クルマや運転手の目線の位置でも変わってくるものの、左端のラインは運転席から「ダッシュボードの中心部」あたりから伸びているように見えているといいます。
車両感覚が破滅的な人は「えっ!? 左端のラインだから、窓の左端から見えてくるもんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それだとラインは実際、クルマのかなり左側にあることになります。
まずはこうした、「固定観念とのギャップ」を埋めるところから始めなければなりません。この固定観念からどうしても脱却できない人は、いつかどこかで思い込みで事故を起こす危険性が高いので、免許返納も検討しましょう。