自動車整備士の資格とは?種類・取得方法・難易度・勉強法を徹底解説【PR】
自動車整備士は自動車の修理やメンテナンスを行う専門職ですが、実は資格がなくても自動車整備の仕事に就くことは可能です。ただし、資格があるとできる作業の幅が広がり、就職にも有利になります。本記事では、自動車整備士の資格の種類や取得方法、試験の難易度、勉強法について詳しく解説します。資格取得を目指す人はぜひ参考にしてください!
【この記事のポイント】
- 自動車整備士の資格と無資格での就業
- 自動車整備士資格の種類とレベル
- 資格取得のための受験条件と合格率
- 資格取得の方法(学校 or 独学)
- 勉強法と試験対策
自動車整備士とは?資格の種類・難易度を徹底解説
自動車整備士とは、整備工場やディーラー、ガソリンスタンド、自動車用品店などで整備や点検、修理を行う、整備士資格保持者を指します。

自動車整備士は国が定めた国家試験に合格することで資格を取得できますが、実は無資格・未経験でも自動車整備の仕事に就くことはできます。整備工場などで働きながら、実務経験を積んで資格取得を目指している人も数多くいます。
無資格でもできる作業は、タイヤやエンジンオイルの交換・板金塗装に関わる作業などですが、携わることができる作業や就職先が限られてしまうので、仕事で自動車整備に携わる人は、資格を持っている人がほとんどです。
自動車整備士の仕事は部品の分解や複雑な整備をするので、知識と技術、経験が必須です。資格を持っている自動車整備士と同じ作業をしたいと思うのであれば、資格取得を目指すことが必要になります。
自動車整備士の資格にも種類があるのをご存じですか?
自動車整備士の資格は難易度の高い方から1級、2級、3級、特殊に分かれており、さらに級ごとに細かい種類に分類されます。

それでは級ごとの特徴を見ていきましょう。
【3級】
・無資格で働きながら資格を取得する場合、3級の資格取得を目指します。
・誰でも受験ができるわけではなく、認定工場や指定工場での実務経験6カ月が必要です。また、整備士の専門学校や高校の自動車・機械に関するコースなどを卒業している場合、実務経験は必要ありません。
・3級は「3級自動車シャシ整備士」「3級自動車ガソリン・エンジン整備士」「3級自動車ジーゼル・エンジン整備士」「3級二輪自動車整備士」に分かれます。
・3級に要求される技能レベルは「自動車各装置の基本的な整備ができること」であり、できる作業はエンジンオイルやギアオイルの交換、タイヤ交換、簡単な整備・点検、上位資格者の整備補助などです。なお、3級自動車整備士は単独でエンジンや足回りの分解整備を行うことはできません。
【2級】
・2級に要求される技能レベルは「自動車の一般的な整備ができること」で、整備工場で行うほぼ全ての整備作業が可能です。
・2級の受験資格は、基本的には3級取得後実務経験2年が必要です。ただし、大学や高校の機械科や自動車科を卒業している人は実務経験期間が短縮されます。また、自動車整備に関する専門学校で2級整備士課程を修了している場合は、卒業と同時に受験資格を得ることができます。
・自動車整備士の8割以上が2級資格保持者と言われており、自動車メーカーの自動車整備士の求人は2級資格必須となっていることも多いです。
・2級は「2級ガソリン自動車整備士」「2級ジーゼル自動車整備士」「2級自動車シャシ整備士」「2級二輪自動車整備士」に分かれます。
【1級】
・1級に要求される技能レベルは「2級自動車整備士より高度な自動車の整備ができること」で、2級よりもさらに高度な知識や技術が要求されます。
・1級は2002(平成14)年度から実施された資格で、保持者は自動車整備士資格者の中でも10%にも満たないと言われています。
・1級は「1級大型自動車整備士」「1級小型自動車整備士」「1級二輪自動車整備士」に分かれています。現在まで1級大型自動車整備士と1級二輪自動車整備士の試験は行われたことはなく、現時点で1級資格保持者はすべて1級小型自動車整備士となります。
・2級までは「ガソリン自動車整備士」「ジーゼル自動車整備士」などに分かれていたのに対して、1級では複数の種類の資格を取らなくても自動車の種別や整備箇所を問わず点検・分解整備などを行うことができます。
【特殊】
・特殊整備士に要求される技能レベルは「各々の分野について専門的な知識・技能を有すること」です。この資格は1級、2級、3級のようにステップアップしていく資格ではなく、各試験を合格すると特殊整備士として活躍できます。
・特殊は「自動車タイヤ整備士」「自動車電気装置整備士」「自動車車体整備士」に分かれます。
・特殊整備士は「この資格がなければ、この分野の整備ができない」というものではありませんが、より高度でその分野に特化したスペシャリストとして就職に有利になるなど、ユーザーなどから信頼される存在になることができます。
2027年1月から自動車整備士資格制度が変わります
国土交通省は、自動車技術の高度化や車両の多様化、そして自動車整備士の人材不足に対応するため、自動車整備士資格制度の見直しを行うと発表しました。この改正により、資格区分や名称が大きく変わります。
まず、これまで1級の資格は「小型」「大型」「二輪」に分かれていましたが、今後は「総合」と「二輪」の2区分になります。
また、2級・3級の「ガソリン」「ジーゼル」「シャシ」「二輪」といった区分も統合され、「総合」と「二輪」に整理されます。
特殊整備士についても名称が変更されます。「自動車電気装置整備士」は「自動車電気・電子制御装置整備士」に、「自動車車体整備士」は「自動車車体・電子制御装置整備士」にそれぞれ改められます。
一方、「自動車タイヤ整備士」については、電子制御装置に関わる整備を伴わないことから、現行制度のままとなります。
これらの新しい資格区分は、2027(令和9)年1月1日に施行されます。
(引用:自動車整備士資格制度等の見直しについて)
資格試験の実務経験も短縮
さらに、2025年7月8日に公布された自動車整備事業に関する法令改正により、整備士資格試験の受験に必要な実務経験も短縮されました。
3級整備士:1年 → 6カ月
2級整備士:3年 → 2年
特殊整備士:2年 → 1年4カ月
この改正はすでに施行されており、より早く資格取得を目指せるようになっています。
(引用:自動車整備士資格の実務経験年数の短縮)
試験は難しい? 合格率は級によって違う! 実技試験が免除されるケースも
国家資格と聞くと、難しいのではないかと思わず身構えてしまいますよね。それでは、合格率はどうなっているのでしょうか?

年度や受験者数、級や種目によってばらつきはあるものの、2024(令和6)年3月に実施された筆記試験では、3級:シャシ67.4%、3級ガソリン:65.6%、3級ジーゼル:57.6%、3級二輪:83.0%、2級では、2級シャシ:86.0%、2級ガソリン:86.8%、2級ジーゼル:93.4%と、2級3級の試験は約70%から90%程度の高い合格率で推移しています。
一方、1級の試験となると59.1%と、2級3級に比べて合格率が大きく下がる結果が出ており、難易度の高さが表れています。(引用:令和5年度第2回[第108回]自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果について)
では、実技試験はどうなのか? というと、実は実技試験が免除される期間に受験するケースが多いため、受験者が少ないのです。
実技試験が免除されるのは以下の2つのパターンです。
・専門学校、高等学校、職業能力開発校などで課程を修了して2年以内の場合
・自動車整備振興会主催の自動車整備技術講習を修了して2年以内の場合
実技試験の合格率も年度と難易度によって振れ幅が大きいですが、2024年1月に行われた実技試験では2級ジーゼルで33.3%、3級ガソリンで57.3%と難易度は高めとなっています。(引用:令和5年度第1回自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果について)
自動車整備士資格の取り方は2通り!学校と独学どちらが自分に合う?
独学? 学校に通う? モデルケースから学ぶ自分に合った勉強スタイルを見つけてみよう
自動車整備士の資格を取得するための方法は大きく分けて2つあります。
・学校に通う
・働きながら独学で資格取得を目指す

学校に通うことのメリットは、最短で自動車整備士になれることと、資格を取得する際の合格率の高さです。
未経験から1級資格取得を目指すには独学の場合、受験資格で実務経験が必要なので最短でも5年6カ月かかりますが、専門学校では最短4年で1級資格を取得することが可能です。そして学校には試験に関するノウハウがあるため、全国平均と比較して高い割合で合格者が出ています。
働きながら独学で資格を取ることのメリットは自分のペースで勉強ができることと、仕事そのものが勉強につながることです。学校に通うことには先ほども挙げた通り大きなメリットがありますが、費用と時間の面が大きなデメリットとなります。独学で資格取得を目指す場合は、勉強と仕事を両立する必要はありますが、費用を大きくカットできます。
先輩たちはどうやって勉強した? 勉強法とコツはこれ!
独学で資格取得を目指す場合など、どうやって勉強をしていいのか分からないという悩みを持つ人もいるようです。
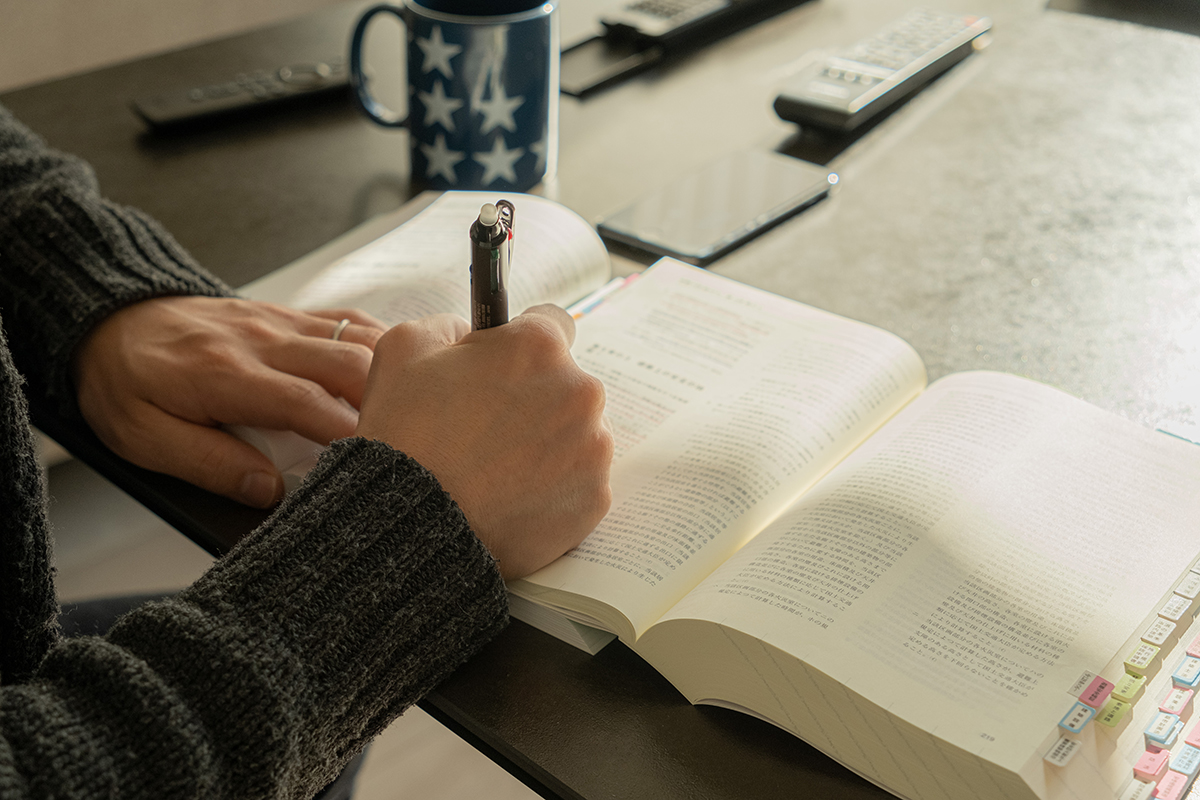
自動車整備士の資格を持つ人から多く聞かれた勉強法は「過去問(過去に出題された試験問題)をひたすら解く」でした。
試験は自動車整備振興会から出ている教科書から出題されますので、それらを読んで過去問を繰り返し解いていくことをメインにした勉強法が効果的です。
過去問を解き、間違えた箇所や曖昧だった部分を教科書や参考書を見直して復習するといった方法で勉強している人が多いようです。過去問は教科書と同じく、自動車整備振興会のサイトに掲載されている他、スマートフォンのアプリなどでもあります。
また、実技試験が免除になると紹介した自動車整備振興会主催の自動車整備技術講習を受けることも、試験対策になるでしょう。
独学で学ぶことにも、学校で学ぶことにもそれぞれメリットとデメリットがあります。
「なりたい未来の自分」を明確にし、自分に合った学びのスタイルを見つけるのが資格取得・自動車整備士への第一歩です。
どちらのスタイルを選んだとしても、焦らずに着実に、ひとつひとつ積み重ねていくことが大切です。














































